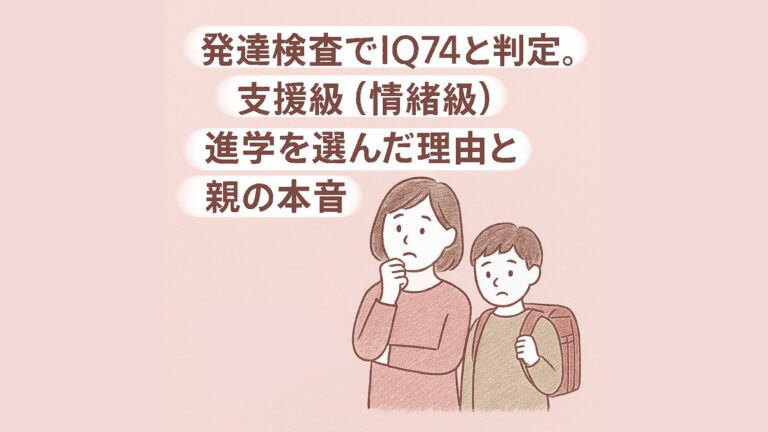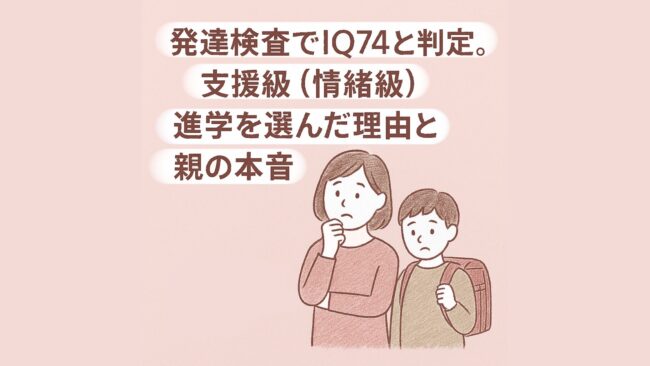
5歳の息子が就学前に受けた発達検査で、IQ74という結果が出ました。
軽度知的障害に近い「グレーゾーン」と呼ばれる領域です。
この結果を受け、私たちは通常級ではなく支援級(情緒級)への進学を決めました。
この記事では、同じようにお子さんの進学で悩んでいる方に向けて、私が体験したこと、感じたこと、そして決断に至るまでの経緯をお伝えします。
WISC-Vでわかった息子の現状
就学前に受けた発達検査はWISC-V。
結果はFSIQ(全検査IQ)74。
公認心理師の先生からは、
- 普通級に通う子どもたちのIQはおおよそ80〜110
- 息子はそれより低く、普通級では困難を感じやすいかもしれない
とのことでした。
「グレーゾーン」という言葉の重み
調べてみると、IQ70〜85は「グレーゾーン(境界知能)」と呼ばれます。
さらに東京ではIQ75以下は知的障害として認定されるそうです。(Xの情報で見つけましたが、私が見つけた東京都心身障碍者福祉センターのページによるとこれは18歳以上の場合に当てはまり、18歳未満の場合は基準が異なるようです。)
今回の息子の結果は75以下で、軽度知的障害と診断されてもおかしくないレベルでした。実際、「知的の診断を出して知的級に入れることもできますよ」と話をされました。
正直、私は「うちの子はグレーゾーンでも上のほうだろう」という希望的観測を持っていました。
しかし、その思いは今回の結果で打ち砕かれました。
やはり、遺伝は強い。
私の夫が診断は受けてないがグレーゾーンの自覚があるという状態です。身内にそういう人がいれば遺伝している可能性は結構高いという事実を突きつけられました。
支援級の選択肢と特徴
心理士の先生によると、知的級は学習面でも個別対応があり、低学年のうちは学習の差が出にくいそうです。IQ74だと知的級・情緒級どちらでも希望できるとのことでした。
息子は「座っていられない」「刺激が多い環境に弱い」という特性があります。
そのため、まずは落ち着いて過ごせる環境を整えたいと考え、情緒級を希望しました。
テストを受ける前は通級制度の利用も考えていましたが、うちの自治体は1年生の1学期から通級は利用できないらしく、支援級か通常級の2択しか選べませんでした。
支援級(情緒級)を選んだ理由
幼稚園での困りごと(立ち歩き、椅子に座れない、全体指示が通らない)は年少から年長にかけてゆっくりですが改善傾向にありました。
3月生まれということもあり、周りより少し幼い部分があってもしょうがないということも考えていましたが、「小学生になったら普通級でやっていけるか?」と疑問に思い、年中のころから担任や市と相談を重ねていました。
年長になり、テストをいざうけてみると結果FSIQ74。WISCの各項目(処理速度、視空間、言語理解、ワーキングメモリー、流動性推理)のばらつきもあり、上は91、下は71。支援級が妥当だと判断しました。
あとは書類を出して市の教育委員会に委ねます。
小学校見学で感じたこと
幸い、校区内には知的級・情緒級が設置されており、事前に小学校見学も済ませていました。
見学した情緒級は1クラス5人に1人の先生がついており、2クラス編成。
支援級はほかにも知的、聴覚などに細分化されていて、昔よりもきめ細かな指導が行われている印象でした。
私が子どものころは「特別支援級」として1クラスしかなく、今のようにニーズごとに分かれている環境はありませんでした。
この変化は、親としてとても心強く感じます。
同じように悩む保護者の方へ
進学先の選択に絶対の正解はありません。
うちの子は今まで乳幼児健診で発達の指摘を受けたことはありません。首のすわり、つかまり立ち、意味のある言葉を話し始めるなどの成長は普通~早いほうでした。
ただ、園での生活の様子を先生から聞いて、私は「うちの子は怪しいな」、「学校生活不安だな」という直感を他人(先生や市の窓口)に相談してよかったと心から思いました。
相談するのに勇気がいりました。何度も何度も話をし続けて心が折れそうなときもありましたし、大丈夫だと言い聞かせることもありました。
相談するためには先生や市、病院から日時の指定をされることの繰り返しなので、かなりの時間を取られます。これはとても大変でした。
大変な思いをした結果、支援につながることができそうです(今から市の教育委員会が決めるので、具体的に決まるのは今冬になります)。
大切なのは、お子さんの“今”に合った環境を選ぶことだと感じます。
そして、親自身の心のケアも忘れないでほしいと思います。つらい気持ち、よくわかります。
私もまだ不安はありますが、息子が安心して学べる環境を選んだことに後悔はありません。
まとめ
支援級への進学はゴールではなく、スタートです。支援級に入れたから安心・・・というわけではありませんね。
これからも息子の成長に合わせて、環境を柔軟に見直していくつもりです。
同じように悩んでいる方が、少しでも前向きな気持ちになれますように。
人によって進学方法はいろいろあると思います。私たち親子の一例としてこの記事を書き残しておきます。